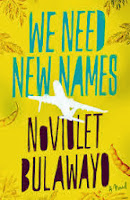2013年がもうすぐ終る。今年はドリス・レッシング、チヌア・アチェベ、そしてネルソン・マンデラが逝った。来年早々にはそのネルソン・マンデラ追悼特集があちこちの雑誌に掲載されることだろう。1950年代にアパルトヘイトに抗して抵抗運動を組織したネルソン・マンデラとその仲間たち。たぐいまれな品格と、その意志と思想の強さで、27年という獄中生活を耐えた人は、南アフリカの抵抗運動、解放運動のシンボルとなっていった。
日本でも古くは60年代初頭に、南アフリカの人びとと繋がろうとする反アパルトヘイト運動が芽吹いた。70年代初めにマジシ・クネーネが来日して当時の若者たちにあたえた「クネーネ・ショック」、それを契機に運動は着実に継続され、ネルソン・マンデラ解放時に最盛期を迎えた。この運動についてはもっと知られてもいいだろう。また当時の日本社会がどんなようすだったかも振り返ってみるのは悪くない。
その運動のおおまかな歴史(日本各地に自発的につくられたグループがあり、それぞれに思い思いのかたちで展開された)を、東京のグループである「アフリカ行動委員会」の実質的中心人物、楠原彰氏がまとめたものがここで読める。
わたしが知っているのは80年代末、そのマジシ・クネーネというズールー詩人の叙事詩の翻訳で悪戦苦闘していたころからネルソン・マンデラが解放され、来日した時代のことだ。それについては中村和恵編『世界中のアフリカへ行こう』(岩波書店 2009)に詳しく書いたので、ぜひ。
特筆にあたいするのは、日本における反アパルトヘイト運動が、それまでわたしが抱いていた「運動」のイメージを快く裏切ってくれたことだ。つまり、組織特有の束縛が一切なく、あくまで自発的個人の意思による活動の場として確保されていたのだ。これは60年代末の全共闘に端を発する運動がセクト化してやせほそり内向きになっていくのを学内でちらちら横目で見ていた者には、じつに新鮮だった。
だから、集団がからきしダメというわたしのような人間もすっと入ることができた。つまり、あの運動は「あ、それ、わたしがやります!」と手をあげて事実やってしまう人間の集まりであり(そのなかでみんな力をつけた)、命令とか指令とか動員とか、上下関係とか、初心者とかベテランとか、先輩とか後輩とか、そういうものとは無縁だったのだ。人と人の関係が、いわゆる「縦系」の縛りから完全に解放されていた。
きみもぼくもわたしもあなたも、来る者はこばまず、去る者は追わず。ほんの数年ではあったけれど、のびのびと、やりたいことをやらせてもらったように思う。自分の仕事ともリンクさせることができたし、大いなる学びの場として、また、面倒な人間関係もおなじ志を仲立ちにしてのりこえ、深めていけることも学んだ。だから、心地よく裏切られたり勘違いしたりしたこともあったけれど、恨みとか怨嗟とは無縁だった。世はバブルたけなわ、喧噪とは縁のないわたしの30代から40代にかけての例外的事件だった。
先日、20年ぶりにそのころの仲間数人とテーブルを囲む会があった。同窓会などとは違って、すっとあの時期に戻っておしゃべりできて、さらに現在この社会で起きていることをも気兼ねなく話題にできた。そういう人間関係。これは貴重。
運動の最盛期、東京を中心に活動していた「アフリカ行動委員会」は「あんちアパルトヘイト・ニュースレター」を毎月発行し、定期購読者に郵送していた。1987年の準備号を出した森下ヒバリ編集長から始まり、つぎの高柳美奈子編集長が第三種郵便にする努力を惜しまず、それを引き継いだ須関知昭編集長の超人的な遠路往復で、1995年まで全85号が発行された。その全ページがその須関氏の努力で「アーカイヴ」にpdf ファイルとしてアップされ、読めるようになった。
あのころの南アフリカと日本の関係がどうだったのか、バブルにわく日本社会の裏側で、南アフリカの解放運動を横目でながめながら、経済的に裕福になった不名誉な、恥知らずの「名誉白人」がどう振る舞ったのか。80年代に白人アパルトヘイト政権下の議員たちと「友好議員連名」なるものをつくり事務局長をやった当時の国会議員、のちに長らく東京都知事をやった人の名前も登場する。あの時代に若者だった人たち、子供だった人たち、そしていま社会の最前線で活躍する人たちが、なにを得てなにを失い、なにを引きずっているのか。
いずれ、各号の「目次」もできるはずだ。そうなれば、もっと使いやすくなるだろう。これはまちがいなく貴重な記録だ。2013年大晦日の、わたしからのプレゼント。
では、みなさま、よいお年をお迎えください。
*****
付記:2017.5.28──昨日開かれた「反アパルトヘイト運動と女性、文学」の場で、アフリカ行動委員会のニュースレターのアーカイヴが移設された先を知ったので、上のリンクをいくつか更新しました。