こんな疑問が「Yahoo」に投稿されたのを見つけた。
Q:クッツェーの恥辱について。オランダに行こうという父親の提案を拒否して、ルーシーが頑なに農村に留まろうとしたのは何故ですか?
以前からずっと考えてきたことだった。『恥辱』が日本語に訳されたとき、多くの読者が感じた疑問でもあっただろう。いまでも解けない謎として立ちあがってくるらしい。
『恥辱』という作品は、クッツェーが多岐にわたる問題を、密度の高い構成と端正な文章のなかに投げ込んだ小説で、人種や、ジェンダー、セクハラ、大学の再編成、ロマン主義思想の問題点、植民の歴史、動物の生命と人間との関わり、などなど、そう簡単に答えが見つからない問題提起が埋め込まれている。とりわけ「動物の生命」については、最後のシーンなど、どう考えていいかよくわからないという人もいる。とにかく優れて「問題含み」の小説なのだ。なかには、問題として読者の意識にすぐに立ち上がってこないほど、深いところに置かれた疑問もある。
また南アフリカという土地にあまり馴染みのない読者にとって、とりわけ若い女性の読者にとって、今回アラートされた疑問は、解けない謎として残ってしまうのだろう。それについてわたしなりに考えてみたい。
『恥辱』という作品は、クッツェーが多岐にわたる問題を、密度の高い構成と端正な文章のなかに投げ込んだ小説で、人種や、ジェンダー、セクハラ、大学の再編成、ロマン主義思想の問題点、植民の歴史、動物の生命と人間との関わり、などなど、そう簡単に答えが見つからない問題提起が埋め込まれている。とりわけ「動物の生命」については、最後のシーンなど、どう考えていいかよくわからないという人もいる。とにかく優れて「問題含み」の小説なのだ。なかには、問題として読者の意識にすぐに立ち上がってこないほど、深いところに置かれた疑問もある。
また南アフリカという土地にあまり馴染みのない読者にとって、とりわけ若い女性の読者にとって、今回アラートされた疑問は、解けない謎として残ってしまうのだろう。それについてわたしなりに考えてみたい。
なぜ南アフリカに帰ってきたか? ここでクッツェーは、人は自分が生まれ育って暮らしてきた土地や社会との結びつきを、そう簡単に切り捨てることはできない、といっているようだ。故国の田舎に小さな農園を買って自給自足の暮らしを営もうとしているルーシーは、やっぱり自分は南アで生まれ育った人間だと思ったのかもしれない。さらりと書かれているが、彼女の「帰国」には、ルーシー自身のなみなみならぬ決意が秘められているのだ。背景としては、作者クッツェーが1970年代初めに、アメリカからやむなく、アパルトヘイト下の南アフリカへ帰国した事情なども重ね合わせることができる。
ルーシーの生活は質素で、大学教授として都会に住んできた父親の暮らしとくらべれば、はっきりいって貧乏暮らしだ。その対比もクッツェーは書きたかったのだろう。それもパートナーの女性が出ていってしまったとあるから、ルーシーはアフリカの田舎でたったひとりで住んでいるわけだ。そんな行動がアフリカの農村社会にとってはどれほど「異質」なものであるか、「奇異」なものであるかは外部からはうかがい知れない。そこもクッツェーは書いている。これは旧態然とした男尊女卑の村社会に、女性があえて(果敢にも)無防備に身をさらすことを意味する。最後はその共同体の規範に従うこと、つまりペトルスの契約上の妻として身柄を保護してもらい(はたしてそれが保護かどうかは疑問だが)、家は彼女の所有として不可侵のものにしたい、とルーシーなりの苦肉の策を解決法として考え出したりするのだ。そのように書くことで、クッツェーは白人女性が「あらたに」アフリカの農村社会に生きることの試みをこの作品に書き込んでいるのだろう。
ちなみに、ペトルスが身内の若者がルーシーへのレイプに関係していたことを知り、ルーシーを「生まれてくる子供ともども面倒をみる」と申し出るところもクッツェーは書き込んでいることに注目したい。それが農村共同体の旧式な、一族の長としての責任の取り方なのだ。(面倒をみる、とか、保護する、とか、結局は「女性を隷従させる」ことを意味するので、女性読者はさらに反発するだろうけれど……)
女性が自立してひとりで生きていくことを許さない社会規範。それは50〜60年前の日本社会を考えてみるだけで容易に想像がつく。先の戦争直後に女がひとりで田舎に古い農家の屋敷を買って住む、と想像してみてほしい。女性は経済的自立ができず、必ず誰かに属していなければならない共同体社会の縛りは、まだまだ世界中のいたるところある。
ちなみに、ペトルスが身内の若者がルーシーへのレイプに関係していたことを知り、ルーシーを「生まれてくる子供ともども面倒をみる」と申し出るところもクッツェーは書き込んでいることに注目したい。それが農村共同体の旧式な、一族の長としての責任の取り方なのだ。(面倒をみる、とか、保護する、とか、結局は「女性を隷従させる」ことを意味するので、女性読者はさらに反発するだろうけれど……)
女性が自立してひとりで生きていくことを許さない社会規範。それは50〜60年前の日本社会を考えてみるだけで容易に想像がつく。先の戦争直後に女がひとりで田舎に古い農家の屋敷を買って住む、と想像してみてほしい。女性は経済的自立ができず、必ず誰かに属していなければならない共同体社会の縛りは、まだまだ世界中のいたるところある。
そもそも17世紀以降、アフリカ南端に入植してきたヨーロッパ系白人、とりわけオランダ系の人たちは、何代も南アフリカに住んできたのだ。ヨーロッパ列強国によるアフリカに対する植民地政策の延長上に、アパルトヘイト体制が誕生したことを思い出してほしい。非白人を徹底的に差別的に搾取するその制度のもとで生きる白人もまた、ある意味、がんじがらめの非人間的な制度下で生きざるをえない状況だった。(といっても、白人が利を得るその制度は、白人にとっては、その非人間性を「自覚」したときに初めて檻となるのだけれど──つまり、見ないことにする、差別などないことにすれば、良心は痛まなかったわけだ。)
 ルーシーは、そんな軛を振り払って、一度はヨーロッパへ向かった。がしかし、オランダへ行っても、母親と折り合いが悪かったのか、南アとは決定的に異なる社会がそこにあって自分を「部外者」だと感じたのか──クッツェー自身がイギリスで『青年時代』に感じたように──とにかく故国へ戻ってきたのだ。
ルーシーは、そんな軛を振り払って、一度はヨーロッパへ向かった。がしかし、オランダへ行っても、母親と折り合いが悪かったのか、南アとは決定的に異なる社会がそこにあって自分を「部外者」だと感じたのか──クッツェー自身がイギリスで『青年時代』に感じたように──とにかく故国へ戻ってきたのだ。
だからルーシーは、自分で決意して戻ってきた南アフリカという土地からそう簡単に逃げ出すわけにはいかないのだ。自分の意思に従えば、これからもずっと住み続けることを選択せざるをえない、たとえ黒人にレイプされてその子供を産むことになっても、というのがこの小説のなかでクッツェーがルーシーに課した役割だ。そういうふうに土地と関係を結ぶ人物として描いた。だからルーシーはある意味、作家ジョン・クッツェーの分身であり、彼の「絶望的希望」のように見えなくもない。
ところが、これを書き上げてから、クッツェー自身は南アフリカを去る。南アフリカにとどまり続ける分身を作品内に刻んでから、その土地を去ったのだ。南ア国内では、そこに批判が集中したこともあった。
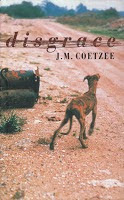 とにかく、この「ルーシー問題」は作品が発表された直後、南アだけではなく世界中のフェミニスト読者のあいだで侃々諤々の議論を呼んだようだ。無理もない。なぜ、歴史的な負荷をひとりの「白人女性」だけに背負わせるのか、という憤懣だ。もちろん南ア国内では、黒人男性が集団レイプする事件を描いたことに対する政権側の批判もあった。だがそれは「新生」南ア社会にとって、当時も今も、あまりに日常的なことでありすぎる「マイナスイメージ」だったからだ、といまになればわかるだろう。(白人男性が有色女性をレイプし続けてきた長い歴史は、ハベバ・バデルーンが論じていた──昨年のちょうど今頃のブログを参照して!)
とにかく、この「ルーシー問題」は作品が発表された直後、南アだけではなく世界中のフェミニスト読者のあいだで侃々諤々の議論を呼んだようだ。無理もない。なぜ、歴史的な負荷をひとりの「白人女性」だけに背負わせるのか、という憤懣だ。もちろん南ア国内では、黒人男性が集団レイプする事件を描いたことに対する政権側の批判もあった。だがそれは「新生」南ア社会にとって、当時も今も、あまりに日常的なことでありすぎる「マイナスイメージ」だったからだ、といまになればわかるだろう。(白人男性が有色女性をレイプし続けてきた長い歴史は、ハベバ・バデルーンが論じていた──昨年のちょうど今頃のブログを参照して!)
この「ルーシー問題」は、しかし、地球規模で人の大移動が起きているいま、「南」と「北のメトロポリス」の関係で考えてみるとき、未解決のさまざまな問題が噴き出る場として、ほとんど普遍的なテーマへと変貌していく。
結局、これだといった答えなどないのだ。歴史的文脈を知り、そのなかで読者がそれなりに考え出すしかない。考え続けていくしかない。それがクッツェー作品を読むということなのだから。
結局、これだといった答えなどないのだ。歴史的文脈を知り、そのなかで読者がそれなりに考え出すしかない。考え続けていくしかない。それがクッツェー作品を読むということなのだから。


