8月1日に封切られたヴィム・ヴェンダースの映画「セバスチャン・サルガド ── 地球へのラブレター」をやっと今日、品川までいって観てきた。
「パリ・テキサス」で4星、「ブエナ・ヴィスタ」で5星だったヴェンダース監督への評価が、残念ながらこの映画で3星に転落した。アフリカに興味をもちはじめたころに出た写真集「An Uncertain Grace」以来、「Workers」をへて「Exodus」までセバスチャン・サルガドという稀有なフォトグラファーの写真に魅入られてきた者として、この映画はちょっと残念だった。
美しい白黒の映像や、サルガドが自分の人生を語ることばは面白かった。この映画の共同監督である上の息子との絡みも面白かった。ブラジルの大きな農園で7人姉妹と育ったこと(大勢の姉妹のなかの一人息子として彼は1944年に生まれている)、とにかく落ち着かない子だったという父親の語り、自給自足の農園生活を15歳まで送ったために貨幣を使ったことがなく、学生として街で暮らしはじめたとき店で食べ物を注文することができず餓えた話、経済を学んでいたとき出会った女性といっしょにあの60年代にパリへ逃げた話、そこで建築を学ぶ彼女と結婚したのち世界銀行で仕事をしたが、カメラに魅せられて、フォトグラファーの道をたどったことなど、とても興味深かった。ほぼ同時代人としてこの地上に生きてきた人間としての共感も感じられた。
仕事はすべてプロデューサー、マネージャーの役割をこなす妻との合作だったときちんと語られていたこともよかった。ほかにも、息子が2人いて下の息子がダウン症だったことなど、ディテールに興味はつきなかった。映画のなかで使われたほとんどの写真は、すでに見ていたものだったけれど、あらためてそのすごさを確認もした。
 しかし、ひとつだけ、とても気になったことがあった。90年代後半の写真のところだ。ルワンダの虐殺、その後のコンゴとの国境につくられた難民キャンプの悲惨さ、さらにコンゴの森に忽然と消えた25万人のツチ系のルワンダ人が半年後に4万という数になってキンサシャにあらわれた話など、その映像は聞きしにまさるすさまじさだ。そのときの心境をサルガドは、自分は「魂を病んだ、救済などこの世にあるのか」と語ったことも衝撃的だった。しかし問題はその直後だ。ヴェンダースが「Heart of Darkness/闇の奥」という表現をべったりと使ったのだ。それが棘のようにこちらに突き刺さり、一気に興が冷めてしまった。コンラッドの同名の小説が出たのは1902年。それから100年以上も後のいま、その表現を無批判に使うヴェンダースという監督の価値観を疑わざるをえなかった。なんという上から目線、ヨーロッパ中心目線。ヴェンダースはともかく、ブラジル生まれのサルガドがそれを許すのか?
しかし、ひとつだけ、とても気になったことがあった。90年代後半の写真のところだ。ルワンダの虐殺、その後のコンゴとの国境につくられた難民キャンプの悲惨さ、さらにコンゴの森に忽然と消えた25万人のツチ系のルワンダ人が半年後に4万という数になってキンサシャにあらわれた話など、その映像は聞きしにまさるすさまじさだ。そのときの心境をサルガドは、自分は「魂を病んだ、救済などこの世にあるのか」と語ったことも衝撃的だった。しかし問題はその直後だ。ヴェンダースが「Heart of Darkness/闇の奥」という表現をべったりと使ったのだ。それが棘のようにこちらに突き刺さり、一気に興が冷めてしまった。コンラッドの同名の小説が出たのは1902年。それから100年以上も後のいま、その表現を無批判に使うヴェンダースという監督の価値観を疑わざるをえなかった。なんという上から目線、ヨーロッパ中心目線。ヴェンダースはともかく、ブラジル生まれのサルガドがそれを許すのか?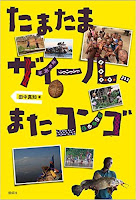 ちょうど、『たまたまザイール、またコンゴ』(田中真知著、偕成社)を読んでいる最中だったこともある。これは日本人である著者が1991年と2012年にコンゴ河を下る冒険譚なのだけれど、この本を読んでいるとまったく別の風景が浮かんでくる。コンゴに生きる人たちの顔が見えてくるのだ。被写体としてのみ存在するわけではなくて、日々、住み暮らす人間としての顔が見える。もちろん平時の顔なのだけれど。
ちょうど、『たまたまザイール、またコンゴ』(田中真知著、偕成社)を読んでいる最中だったこともある。これは日本人である著者が1991年と2012年にコンゴ河を下る冒険譚なのだけれど、この本を読んでいるとまったく別の風景が浮かんでくる。コンゴに生きる人たちの顔が見えてくるのだ。被写体としてのみ存在するわけではなくて、日々、住み暮らす人間としての顔が見える。もちろん平時の顔なのだけれど。
一方、サルガドは紛争のさなかに飛び込んで行って、極限状態の人間を写真に撮る。だから衝撃度、緊迫感が、一枚一枚の写真のなかにすさまじいまでに宿る。その違いは決定的だ。しかし……。
『たまたまザイール、またコンゴ』では、コンゴがなぜかくも自立不能の国なのか、鉱山資源をめぐる紛争に世界各国の利権がからむ構造もきちんと見える展開がある。さらにティム・ブッチャーという作家の本『Blood River』に出てくる逸話が、コンゴの悲惨さを脚色するための嘘だったということも露見するのだ。
『たまたまザイール、またコンゴ』では、コンゴがなぜかくも自立不能の国なのか、鉱山資源をめぐる紛争に世界各国の利権がからむ構造もきちんと見える展開がある。さらにティム・ブッチャーという作家の本『Blood River』に出てくる逸話が、コンゴの悲惨さを脚色するための嘘だったということも露見するのだ。
今日観た映画では、サルガドは偉大なフォトグラファーであることが淡々と描かれる。彼の素顔に迫ろうとする意図も理解できる。その精神の旅路もまた面白い。しかし……。それらの写真を撮るまでに至った、当然そこにあったであろう現地の人間たちとのやりとりや関係が、まったく見えない。あるいは「Workers/労働者」を撮るなら、なぜ、自分の農園の労働者の話はでてこないのか。これは映画の限界なのか。その部分は落として構わないと判断されたのだろうか。そこが理解できない。そして残念だ。この不満は彼の自伝を読むことで満たされるのだろうか。
読んでみよう、彼の自伝。
*******************
付記:アフリカで病んだ精神を大地が癒してくれたというサルガドは、次に、大地と生き物の創生へと関心を移していく。荒廃したサルガド農園に植林をして青々とした森を取り戻す。そのプロセスはすばらしい。しかし、その農園がもともとだれの土地だったか、と自問するところはこの映画にはない。自伝にはあるのだろうか?
読んでみよう、彼の自伝。
*******************
付記:アフリカで病んだ精神を大地が癒してくれたというサルガドは、次に、大地と生き物の創生へと関心を移していく。荒廃したサルガド農園に植林をして青々とした森を取り戻す。そのプロセスはすばらしい。しかし、その農園がもともとだれの土地だったか、と自問するところはこの映画にはない。自伝にはあるのだろうか?















