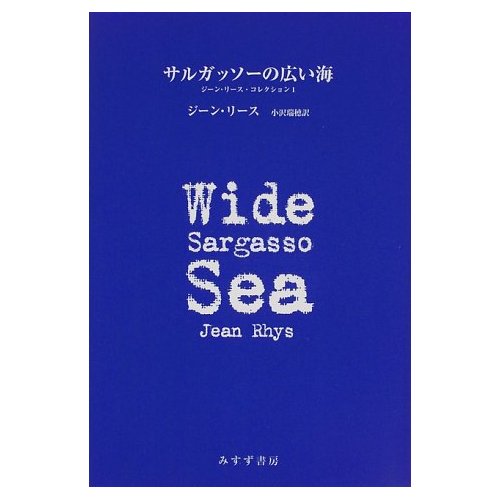 いまは古書でしか入手できないようですが、今月から刊行が開始される「世界文学全集」(河出書房新社)の第2期に入ることになった、ジーン・リース著/小沢瑞穂訳『サルガッソーの広い海』(みすず書房刊、1998年)。
いまは古書でしか入手できないようですが、今月から刊行が開始される「世界文学全集」(河出書房新社)の第2期に入ることになった、ジーン・リース著/小沢瑞穂訳『サルガッソーの広い海』(みすず書房刊、1998年)。紙幅の関係で、以前書いた書評では触れることができませんでしたが、中村和恵さんによる巻末の解説が秀逸です。中村さんはその後、リースをめぐる大変興味深い文章をいくつも発表しています。カリブ海文学を考えるとき、この作品はとても面白い位置にあります。映画にもなりました。
*********************
シャーロット・ブロンテの「ジェーン・エア」といえば、一昔前はだれもが読んだイギリス小説の古典といえるだろう。私はまず小学校の図書室で見つけた少女版──たしかタイトルは『嵐の孤児』(すごいタイトル!)──で読み、つぎに中学のころ、家の書架に並んでいた世界文学全集で再読した。そこには、孤児院を出たジェーンを家庭教師として雇い、やがて彼女に結婚を申し込む、口ひげをたくわえたお金持ちの紳士、ロチェスターなる人物が登場した。
だが本書は、そのロチェスターの最初の妻、ジャマイカ出身の女性の目から書き改められた物語なのだ。狂女さながらに屋敷の屋根裏に幽閉されていた、あのバーサである。
十代の私は「ジェーン・エア」をどのように読んだか。伯母一家から虐待され、孤児院では極貧と厳格な規律に苦しめられ、ようやく安定した職をあたえてくれたロチェスターの愛を得たのも束の間、重婚しようとした氏のおぞましい経歴を知り……と波乱万丈のジェーンの生涯に自分を重ね、夢中になって読みふけったのではなかったか。そのように読めるストーリーのなかで、植民地生まれのこの「忌まわしき狂女」は、ジェーンの幸福を邪魔する、不気味な存在として脳裏に焼きついていた。
けれども、その女性の側からしてみれば、本国からやってきて、彼女の遺産目当てに結婚したこの名門の男性こそ、支配欲、無理解、放蕩、自己憐憫を絵に描いたような典型的イギリス人ということになる。彼女のほうは、生まれた土地から、根こそぎむしりとられるようにして連れ去られ、軟禁され、家に火を放って狂死するのだから。イギリスという異郷=帝国は、決して彼女をありのままには受け入れることはなかった。アントワネットという名前さえ、一方的にバーサと変えられてしまった。
作者のリースは一八九〇年、カリブ海のドミニカ島に生まれたクレオールの作家だ。ヨーロッパ植民者の系譜だが、カリブの風と暑熱を全身に吸い込んで育った。黒人になりたかった、白人の、女性の、作家である。この幾重にも屈折したスタンスが、彼女の生まれた時代とともに、解き明かされるのを待つ混沌といった魅力を、この作品にあたえているように思える。
とはいえ、作中、私がもっとも共感をおぼえたのは、オービア(魔術)を使う元奴隷のクリストフィーヌといいう黒人女性だったのだけれど。
さまざまな意味で、いま、世界を見るときに不可欠な、視座の転換を確認できる作品である。
***************
付記:1999年1月24日付「北海道新聞」に掲載されたものに加筆しました。